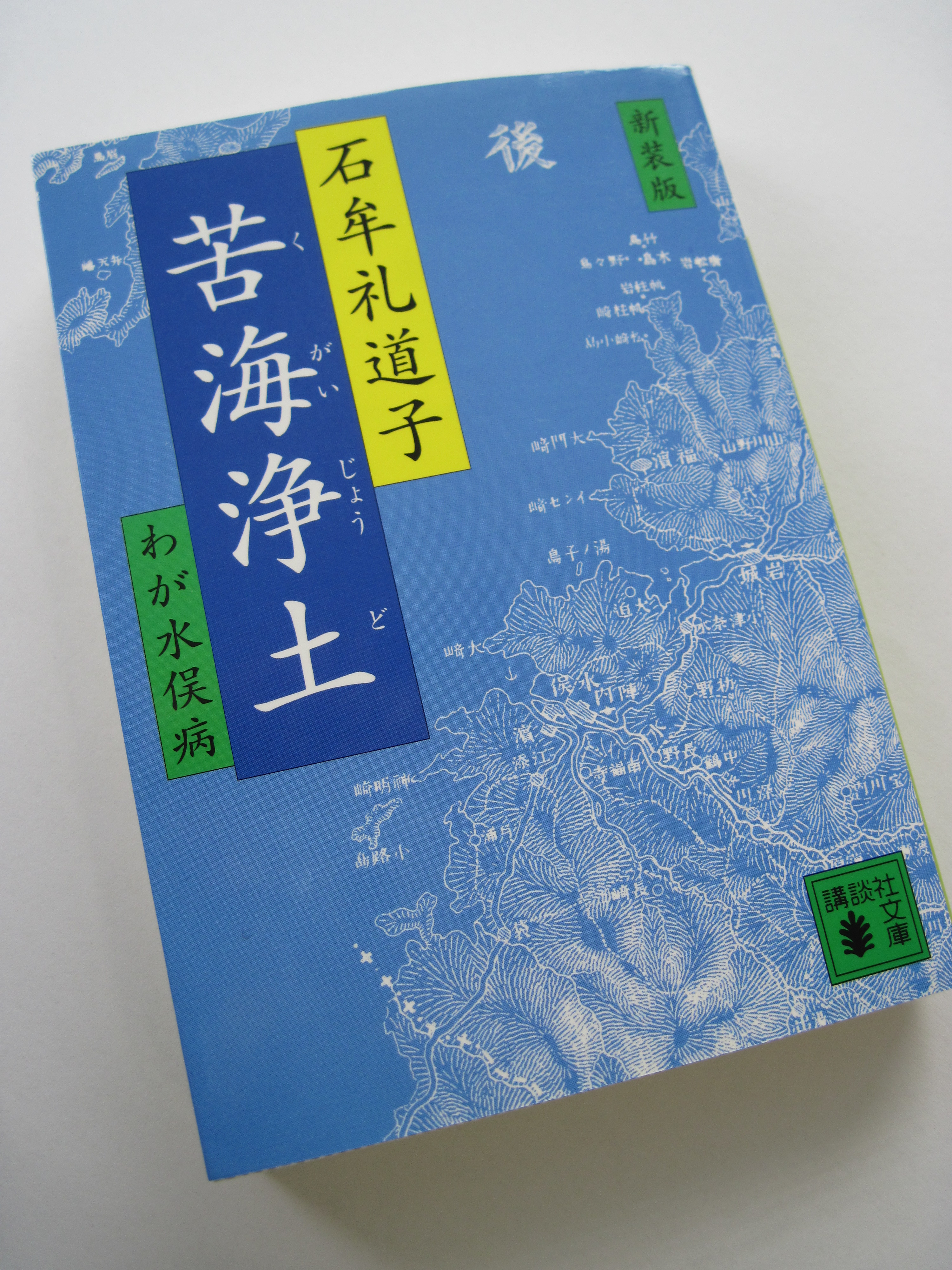▶「記録しなければならぬ」という衝動
石牟礼道子(いしむれ・みちこ)さんが亡くなった。
水俣病の患者を描いた著書『苦海浄土』(くがいじょうど)はあまりにも有名で、いまさらこの私が何を語ろうが、稚拙な話になってしまうことは間違いない。
しかしこれだけは触れておきたい。『苦海浄土』の中の一文が、私の心中に大きなうねりを立ち上げて止まないという事実である。
その一文は、第三章「ゆき女きき書き」の「水俣市立病院水俣病特別病棟X号室」と始まる「五月」という節の中にある。
挙げてみよう。
「わたくしが昭和二十八年末に発生した水俣病事件に悶々たる関心とちいさな使命感を持ち、これを直視し、記録しなければならぬという盲目的な衝動にかられて水俣市立病院水俣病特別病棟を訪れた昭和三十四年五月まで、新日窒水俣肥料株式会社は、このような人びとの病棟をまだ一度も(このあと四十年四月に至るまで)見舞ってなどいなかった」
「悶々たる関心」「ちいさな使命感」「記録しなければならぬという盲目的な衝動」という言葉にジャーナリストの魂を揺さぶられ、私はジャーナリストとして何も成し遂げていないじゃないか、との強い自己嫌悪に陥る。
石牟礼さんは2月10日の未明、90歳で逝った。熊本県の天草に生まれ、生後まもなく対岸の同県水俣町(現・水俣市)に移り住んだ。そこは美しい自然があふれ、精霊の住む土地だった。
▶想像力の射程にとらえて書く
恥ずかしながら10数年前まで石牟礼さんをよく知らなかった。
水俣病が公式確認されたのが、1956(昭和31)年5月1日。その確認から50年後の産経新聞(2006年5月3日付)に「水俣病50年」というタイトルの社説を書いた。
このとき取材資料のひとつとして講談社文庫の新装版『苦海浄土 わが水俣病』=写真=を買い求め、石牟礼さんの存在のすごさを知った。
驚いたことに、その文庫本の巻末に掲載されている雑誌「熊本風土記」の編集者で石牟礼さんと親しかった評論家の渡辺京二氏の解説によると、『苦海浄土』は患者からの聞き書きでもなく、ルポルタージュでもないというのだ。
石牟礼さんは生まれ育った境遇と彼女の文学的才能によって崩壊して引き裂かれる水俣病患者とその家族の意識を、忠実な聞き書きなどによらなくとも、想像力の射程にとらえることができたというのである。
想像力で書くとなると、これはもうジャーナリズムではない。取材相手のひと言ひと言を漏らさず頭に入れ、ノートに取り、録音もする。一般的にはこれが新聞記者をはじめとするジャーナリストの仕事だと思われている。
しかし誤解を恐れずに言わせてもらえば、新聞記者も想像力で記事を書くことがある。
肉親を事件や事故で失い、言葉を発する力もない取材相手の気持ちを推し量って字にする。インタビュー中に自分をうまく表現できない目の前の相手の顔色や動作の変化を丁寧に観察して心の内を探り、それを記者の言葉で綴る。
石牟礼さんが渡辺氏に「あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだ」と話していたというが、よく分かる。
石牟礼さんは本物のジャーナリストだったと思う。
▶「利益最優先」という怪物
ところで「水俣病50年」の社説には「想起したい『不作為』の罪」という見出しを付けた。
冒頭はこう書いた。
「古くはカドミウム汚染の『イタイイタイ病』、石油化学コンビナートの排煙などによる『四日市ぜんそく』、そしてメチル水銀中毒の『水俣病』が、公害病と認定され、最近では『ダイオキシン』や『アスベスト(石綿)』が問題になっている。公害や健康被害は繰り返され、なかなかなくならない」
最後は「健康被害や公害はどれも行政、企業の対応遅れと不作為で広がった」と指摘し、「行政は被害を小さく見積もり、大したことはないと保身に走ってはならない」と主張した。
公害は高度経済成長を遂げた日本の社会の負の落とし子である。それに気付くには長過ぎるほど時間がかかったし、公害に対する反省心を失うと、再び深刻な事態に見舞われる。
「サリドマイド」や「薬害エイズ」などの薬害も同じ構図で繰り返されてきた。
石牟礼さんは高度経済成長を支えた利益を最優先する考え方を本能的に嫌悪した。まさに有機水銀で不知火海を侵したチッソ水俣工場はその象徴だった。利益最優先という怪物は自然を破壊し、人の心をさいなむ。彼女はそれを訴え続けた。
石牟礼さんを一度、取材したかった。
木村良一(ジャーナリスト)
参考…「水俣病」については2013年11月号で「水俣条約をきっかけに公害について考えよう」という見出しを付けて一度、書いています。
http://www.tsunamachimitakai.com/pen/2013_11_002.html