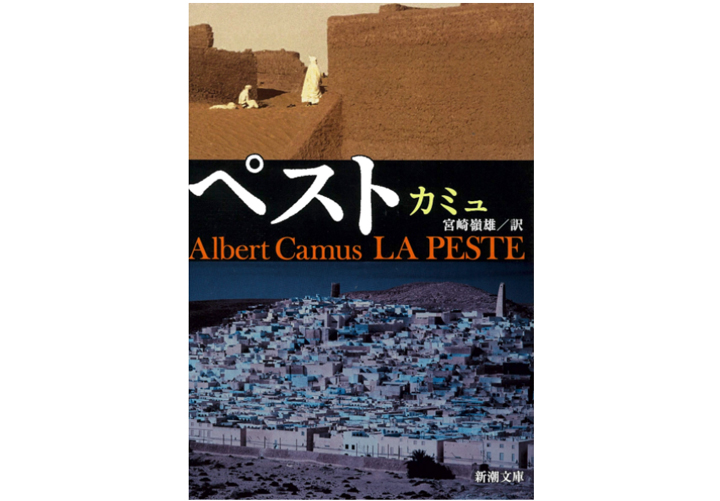「ペスト患者であることはひどく疲れることなんだ。しかし、ペスト患者になりたくないと望むことは、さらにもっと疲れることなんだ」
「絶望に慣れることは、絶望そのものより悪いのだ」
これはフランスのノーベル文学賞受賞者カミュ(1913~1960)の代表作「ペスト」に出てくる言葉だ。
ペスト蔓延の当時フランス領アルジェリアの海浜都市オラン、ペストの流行で街が完全に封鎖される。この突然の平常な生活に舞い降りた不条理にどう立ち向かって行くのか?
「ペスト」(新潮文庫)は版元の新潮社によると、2月からのコロナ騒ぎの中で16万部も増刷して、今や30万部に届く勢いだという。身に迫るコロナの気配が、この勢いを生み出しているという。その売れ行きは世界的な現象のようだ。
書かれたのはカミュが34歳の時、第二次大戦中の対独レジスタン運動を経て、1947年に刊行された。日本でもすでに60年をかけて百万部を超える静かなベストセラーとして、いわば文学好きの学生たちの“不条理の文学”の通過儀礼として読み継がれてきている。
もちろんオランでの「ペスト」はフィクションであり、「ペストが象徴する災忌は、パンデミックだけではなく、天災のみならず、戦争をはじめとする人間が作り出す不条理を象徴している」と指摘するのはNHK出版の「100分で名著―アルベール・カミュ『ペスト』」の著者・学習院大学・中条省平教授(仏文学)。
当初主人公の医師は身近に見た患者からペストを疑い、市役所、医師会に報告する。市長以下幹部はペストという言葉すら、認めようともしない。しかしペストは進行して死者は続出。県当局は都市のロックアウトを宣告する。軍隊が市の道路を固め、郵便物さえシャットアウトされ、外部とのやり取りは電報だけになる。
1年近い都市封鎖の中で市民は、「あまり長くは続かない、あまり馬鹿げたことだから」と希望的観測の中で生きようとする。カフェやレストランは混雑し、オペラ劇場も満員盛況。しかし、オペラの最中、歌手が突然ペストの発症で舞台上で崩れ落ち、観客は騒然となり、逃げ惑う。
最初は二桁台の死者だったが。三桁台となる。市民は競技場などに置かれた隔離病棟を目にし、感染を恐れて立会いも許されない埋葬。「ペスト」の現実に向き合わざるをえなくなる。
主人公医師リウは「絶望に慣れることは、絶望そのものより悪いのだ」という。しかし人々は追放と監禁状態のなかで、過去や未来という時間の展望が失われ、未来を奪われた囚人のようになっていく。絶望に慣れていくのだ。そして自棄になった人々による放火や略奪がおきる。
その一方で医者リウを中心とする登場人物たちは、ペストに立ち向かっていく。
偶然取材で訪れていた新聞記者は、大金を払い封鎖から逃れてパリに待つ婚約者のところに行こうとする。しかし決行寸前になって「もし自分が出て行ったら恥ずかしい気持ちになるだろう。そうなったら、残してきた彼女を愛することの妨げになる」とリウに語り「保健隊」に参加する。
裁判所の判事は自分の幼い子供がのたうち回ってペストで死ぬのを体験して、隔離病棟でのボランティアを志願する。
リウの友人のタルーは「私はずっと以前からペストに苦しんでいた」と告白する。彼の父親は判事で何件かの死刑判決を下していた。人間に死をもたらす病気であれ、死刑判決という社会的な死であれ殺人であり、ペストと同意義だというのだ。
カトリックの神父は当初、「ペストは神が下した天罰」と説教する。しかし残酷な患者達の死に際に立会い、神の存在に揺らぎを感じる。
医師リウは「もし自分が全能の神を信じていたら、人々を治療するのを辞めて、人間の面倒を全て神に任せてしまう」と無神論の立場を表明する。この不条理の「ペスト」に囲まれた世界の中での神学論争、実に興味深い。
そして「ペスト」の終息。街が解放され歓喜に沸き返るその時、殺人犯で逃亡してオランにいたコタールはペストがなくなれば逮捕される、マンションの窓からピストルを乱射し警官隊に射殺される。ペストがなくては生きられない人間の存在を描き出す。
カミュは、実存主義のサルトルとの有名な1952年の論争で、殺人さえも乗り越える暴力革命による不条理の解消を許すサルトルと、人間主義的な反抗によって不条理を解消すべきと主張する。ソ連邦の社会主義が知識人の中で圧倒的に支持された戦後の時代、この論争でカミュはサルトルに論破される。
ソ連崩壊という現実を見た我々は、カミュの主張の正しさを読み取ることができた。しかし中国のような全体主義国家のありようが、コロナ制圧に効果があったとされる中で、どうカミュの言う人間主義的な反抗によって、コロナウイルスを封じ込めることができるのだろうか。
この「ペスト」は不条理に立ち向かう人間としての在り方を問うたものだが、その思考としての深さは尋常ではない。なるほど1957年、ノーベル文学賞を受けたのもうなずける。
いま「新型コロナウイルス」という、不条理な病原体によってロックアウト状況下の全世界。その制圧にどう立ち向かうのか、「ペスト」の問いかけは決して古くない。今まさに読まれるべき作品ではないかと思う。
桃井一郎(元全国紙経済部、ジャーナリスト)